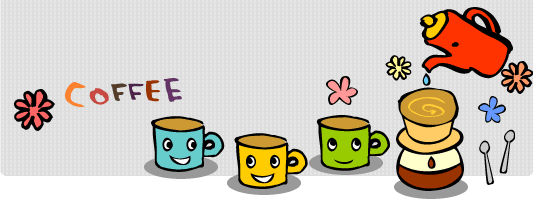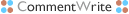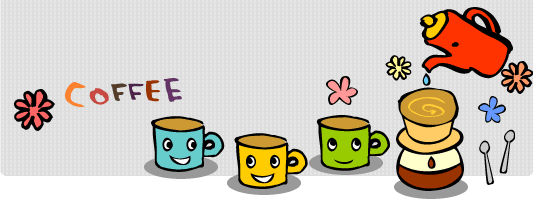[サウンド・マーケット]民放FM,1983年1月13日
<スピノザ・トロペイ・ナイト・1~ダイレクト・サウンド→ニューヨーク'83・4>
デビッド・スピノザとジョン・トロペイ。


○ニューヨーク・ギター by デヴィッド・マシューズ
○13日の金曜日 by スピノザ
○エッジ・オブ・ザ・ソード by スピノザ ※マイク・マイニエリに捧げる曲
デヴィッド・スピノザg、ジョン・トロペイg、アラン・シュワルツバーグds
ニール・ジェイスンb、クリス・バルマーkey、ジミー・メイレンperc
'82年11月11日、ニューヨーク、セブンスアヴェニューサウスにて
この日もキキ・ミヤケさんが出演して長い話をしています。
この二人のライブについて、レコーディングで一緒にすることはあるけど、ライブでは聞いたことがない。
ライブでは3年ぶりくらい、と、話してました。
ほかにも興味深い話をしていたので聞き取ってみました。
どうして、たとえばスティーブ・ガッドみたいなのが引っ張りだこかなっていうのはあるんだけれども、ただプレイできるだけじゃ、もちろんそれはベーシックにできなきゃいけないことなわけで、彼の場合なんて言うのは、それがいろんなことができるから、もちろん仕事が入るわけだけども、まぁ、あのー、ユーモアのセンスね。
おっかしくないとやっぱりスタジオの仕事っていうのはヘビーになっちゃうから、やっぱり何時間も何時間も缶詰めになって、まぁ人のレコードですよね、簡単に言っちゃったら。
やっぱり6人とか7人のリズム・セクションで固めていかなきゃいけないのに、「ちょっと、じゃぁやり直し」ってプロデューサーがまたそこで考え込んで、そこで1時間待たなきゃいけないとか。
まぁそこで外へ出られないし、やっぱりそこでバカなことを言ったりして雰囲気を楽にしないとやっぱり続かないですよね。
だから、そういう意味で、たとえば、スティーブだとかスピノザとか、ブレッカーの兄弟たちっていうのはもうおかしいわけ。
ですから、N.Y.のスタジオ・シーンの独特のユーモアのセンスっていうのがあるわけ。
テクニックだけじゃダメというのがよく分ります。
音楽志向が共通することも大事だけど、結局は人間関係が一番大きかったり。