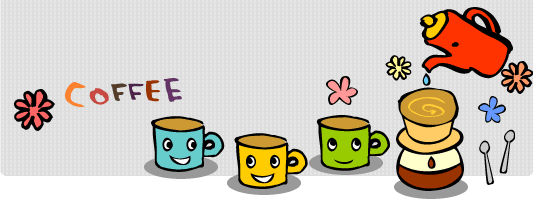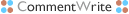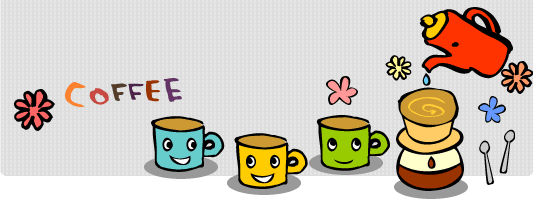[グッド・ヴァイブレーション~渡辺香津美のドガタナ・ワールド]
<松岡直也を迎えて>民放FM1983年3月12日
さらに続きます。


○マジック・ナンバー
ハービー・ハンコック
渡辺:えー、曲が変わりまして、ハービー・ハンコックのマジック・ナンバーという。これは最初結構ファンクっぽいんですけども、
松岡:そうなのね、結構ファンク。で、途中からね、あのー、いわゆるあのー、パーカッション、ラテンのパーカッションをね、ちゃんと使った、いわゆるリズム・セクションていうのがね、あんまり取り入れないんですね、あのー、ジャズ・マンでも。
渡辺:そうですねぇ。
松岡:うん。あのー、それがね、どういうわけかハービー・ハンコックが2回続けてんですよ、それをね。それの中の、このまぁ一曲なんだけどね。途中から変わるんだね。
渡辺:途中から変わるコロっと。そうなんですか。
松岡:ちゃんとね、あれ、いわゆるあのーパーカッションの要素だけじゃなくてね、フュージョン・パーカッションじゃなくてちゃんとしたパーカッション使った
渡辺:いわゆるあのー、なんて言うのかな、モントゥーノの遊び、リズムのね。
松岡:そうそうそうそう。モントゥーノ。
渡辺:そういうパターンだけベースで借りて、あとはいわゆるシックスティーンみたいにして、パーカッションとか全然入れないでやったりするのときどきありますけどね。そのー、完璧にそういう、 ジャズっていうか
松岡:そう。うん。モントゥーノを完全にやってますよね、これも。
渡辺:いや、この間ね、リズムのなんかね、カタログっていうレコードがあったんでね、2枚組でね。中もソ連の舟歌のリズムから、それからロックからジャズからとかね、ラテンのリズムとかいろんなのがこうちょっとずつ入ってんですよ。20秒とか30秒ずつ。で、あのー、わりとね、あのー、なんか珍しそうなレコードのやつをね、入ってんのね。ちょっと抜粋してあったりとかして。やっぱしラテンっていうのはリズムの宝庫だなと。すごいですね。2枚組の1枚と半ちょっとそれで占めちゃってますね。
松岡:そんなにあるかなぁ。結構ねぇ。
渡辺:後、あのー、サルサっていうかね、そのグルーブ、聞いてて面白かったのは、ソロ・プレイヤーみたいなのがね、たとえばピアニストがリズムを刻んでいるときってのはトゥンカトゥンカトゥントゥンみたいにやってて、自分のソロになると突然ね、チック・コリアみたいにどんどんジャズに発展していっちゃったりとか。
松岡:あぁ、やっぱりジャズの影響が強いんじゃないかと思うんだけどね。
渡辺:あれはやっぱりソロに関してはその人が好きにやるっていう、で、いわゆる伝統音楽みたいに形が決まっているというのは。
松岡:だいたい決まっているんだけど、あのー、いや、あのやっぱり決まってんじゃないかね。うん。決まってるんだけど、強いアクセントになった場合はちゃんと決まってくるだろう。あとは最初のインプロバイズは結構ね、好きにできるんじゃないかな。
渡辺:そこでやっぱり、なんて言うか、ジャズとラテンとのなんかフュージョンみたいなのが、
松岡:うん。出てくるしね。
渡辺:逆に松岡さんの場合はラテンのほうからジャズ的なものにアプローチするっていうことなんかやっぱりありますか。
松岡:う~ん、まぁアプローチしても、限界があるからね。
渡辺:そのー、たとえばロックみたいなほうに興味なんていうのはありますか?いわゆるなんていうか、
松岡:うん、あるよ、それはね。
渡辺:いわゆる、そのー、ヘビー・メタルとかね。ハード・ロックとかジミヘンとかそういうの。
松岡:そこまではちょっと、できないからね。
渡辺:じゃああのー、僕はね、そのー、いわゆるラテンっていうね、その音楽に最初、僕自身がそんなかでやった時の考えてみると、子供の時にね、ラテンってのが、ザビア・クガート。
松岡:ザビア・クガートね。
渡辺:えぇ。レコードをね、うちの親父が持ってるのをかけて。やっぱり、エル・クンバンチェロとかね。クマーナとか。
松岡:あれはね、いわゆるフュージョンなんだね。
渡辺:もうすでに。
松岡:うん、すでに。ああいう音楽に、を、好んでいたら、少し、こうなんていうかね、幅広く音楽がね、分かってたですね。意外とあれをばかにしてたの、僕なんか。
渡辺:あぁ、そうですか。
松岡:あの辺はちょっとね、あれはポップスじゃないかとかね。
渡辺:あー。
松岡:歌謡曲じゃないかとか。僕らはばかにしてたよ。
渡辺:いわゆるそのー、なんか生粋のといったら変だけど、そういう と違う雰囲気
松岡:あれはちゃんとしたセッションがないでしょう。モントゥーノの。
渡辺:あっ、そうですね、言われてみれば、やっぱ。
松岡:きれいに流れてるでしょう?
渡辺:メロディー志向ですね。
松岡:そうそうそうそう。きれいに流れてる。
渡辺:で、いわゆるこう、最近になって、最近っていうか、十年くらい前になると思うんですけど、ふたたびずっとジャズとかウェス・モンゴメリーとかそういうのばっかりやってて、それで、再びラテンっぽいの聞いてっていうのがね、サンタナがね、出てきたときに。
松岡:あっ、サンタナ。うん。
渡辺:これはなんかね、今までのロックと全然違うね、感じだなって思って。
松岡:うん、サンタナがね、ロックだけやってるのはあんまり好きじゃないのね。だけど、やっぱりサンタナはラテンのちゃんとしたリズム・セクションで、そのスウィングしているときのフィーリングね。あのフィンガリング。フィンガリングから何やら。すごいイントネーション。
渡辺:そうですねぇ。
松岡:伝わってくるものがありますよね。
渡辺:それであと、あのー、日本に来た時、 ていうか、パーカッションなんかね、すごい人が入っている
松岡:入ってる、入ってる。で、日本に来た時もアルマンド・ぺラサが、
渡辺:そうですね。
松岡:僕がやったことあるんですよ、アルマンド・ぺラサ。
渡辺:あっ、そうですか。
松岡:うん。だいぶ前だけどね、それは。ジョージ・シアリングが来た時に。
渡辺:ジョージ・シアリング。
松岡:うん。アルマンド・ぺラサを連れてきてね。そんときやったんだよね。
渡辺:それ、あのー、とにかく見ててね、すごいリズム・セクションだなぁと。
松岡:うん、あれもちゃんとしたリズム・セクションだよ。そんなかで、やっぱりそんなかでやってるサンタナっていうのは良いと思いますね。
渡辺:また、生き生きしてますね。
えー、今かかっているのは、そのー、さっきのハービー・ハンコックとサンタナと一緒に共演している「サタデイ・ナイト」という。しばらく聞いて下さい。
○サタデイ・ナイト
ハービー・ハンコック
○ア・シ・ソイヨ
ラリー・ハーロー・オーケストラ
渡辺:えー、この曲は、じゃあ松岡さんに紹介していただきたいですけども。
松岡:これは、ラリー・ハーロー・オーケストラの「ア・シ・ソイヨ」という曲なんです。
渡辺:「ア・シ・ソイヨ」。どういう意味なんでしょう?
松岡:分んないんだね、どういう 。
渡辺:ラテン語なんかあれなんですか?やれ
松岡:分んないんだ。
渡辺:研究だから
松岡:全然そういう。不勉強だからね。香津美どう思う?この「ア・シ・ソイヨ」。
渡辺:いやー、さっきからずっと見てね。えー、速くない、足が速くなくて足が遅いよ、つって。
松岡:あっ、なるほど。
渡辺:曲は早いですよね、でも。
松岡:うん、曲は早いね。
渡辺:これはもう、いわゆるもうなんて言うか生粋の
松岡:うん、サルサですね。うん。で、あのー、それでちょっとね、やっぱ軽い良さがあるっていうかね。ラリー・ハーローの場合。
渡辺:あのー、ニューヨークに行ったときなんかに、あのー、ちょうど、一昨年だったかなぁ、サルサ・オールスターズでしたっけ?
松岡:あっ、ファニア・オールスターズ。
渡辺:ファニア。ファニア・オールスターズ。カーネギー・ホールかなんかで、
松岡:カーネギー・ホール。うん。
渡辺:コンサートがあったみたいですね。
ニューヨークはマジソンのとこで夏になると
松岡:すごいね。
渡辺:カーニバルみたいで、すごいですね。
松岡:もう、サルサのスターがね、勢ぞろいで。
大体まぁ、あのー、サルサの場合ボーカル、アーティストによってね、あのー、バンドが組まれていくんだけどね。
渡辺:ボーカルが中心?
松岡:中心ね。
渡辺:ああいうやっぱりこう、なんか、カーネギー・ホールで見るっていうのは、なんか、(笑)、面白いもんですね。
松岡:面白いねぇ、うん。
渡辺:しぶいなぁ。
松岡:自分もやっぱプエルトリコ人とかね、なんかそういう風になったような気分になっちゃうのね。
渡辺:うん。
「ア・シ・ソイヨ」、聞いていただきたいと思います。
PR